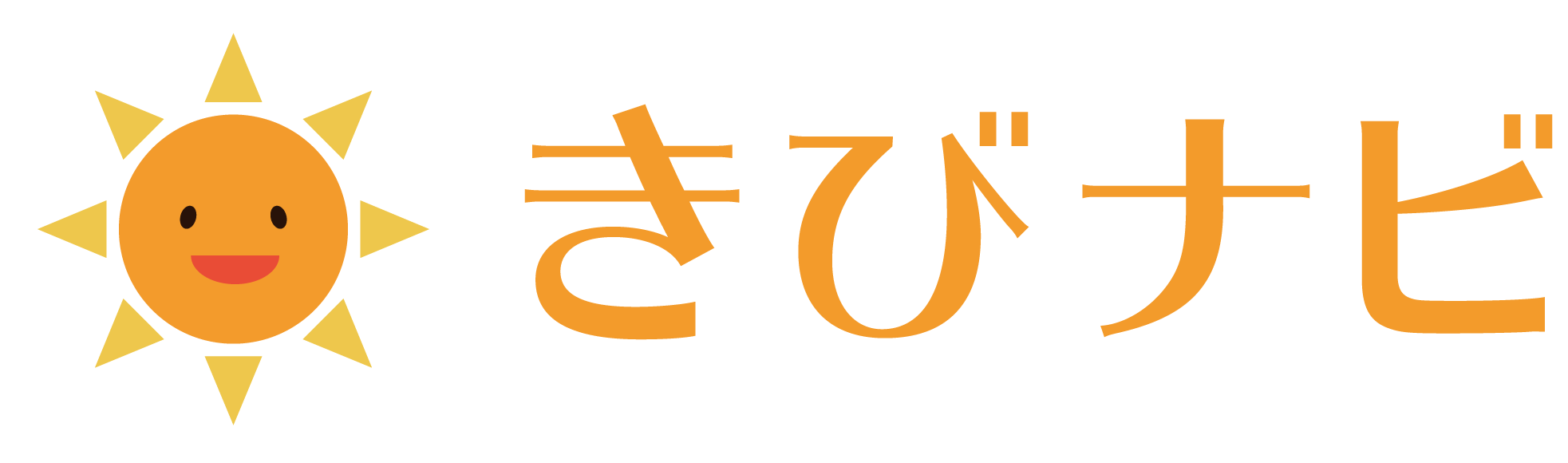当サイトを閲覧くださいまして、誠にありがとうございます。
運営者のアサノ(@asnyskJP)と申します。
簡単に私の自己紹介と当サイトの紹介をいたします。
運営者 アサノのプロフィール
Illustration by Zoe
お仕事についての詳細は下記をご覧ください。
 非公開: 広島県福山市/岡山県のライター・アサノの仕事内容、仕事のご依頼
非公開: 広島県福山市/岡山県のライター・アサノの仕事内容、仕事のご依頼
もくじ
運営者 アサノの略歴
![]()
初めての一人暮らしをする。
学部は経済学。
消費税が3%から5%に増税。
長野新幹線 高崎〜長野駅間が開業。
神戸連続児童殺傷事件が発生。
業種は食品販売業。
就職超氷河期のため、条件面や希望職種など希望とはかなりかけ離れており、妥協をしての就職だった。
小泉純一郎が内閣総理大臣に就任。
愛子内親王が誕生。
アメリカ同時多発テロが発生。
長時間労働と休日の少なさ、希望職種への異動が困難なことが原因。
離職後、就職活動のかたわら、Web制作などを専門スクールに通い学ぶ。
HTMLの知識やDreamweaver・Photoshop・Illustratorなどのソフトの使い方を学習した。
ソルトレイクシティ冬季オリンピック開催。
FIFAワールドカップが日韓共同で開催。
多摩川のアゴヒゲアザラシ「タマちゃん」が人気に。
業種・職種は鉄鋼業の工場作業員。
ブラジル人やフィリピン人に交じり仕事をする。
朝青龍が第68代横綱に。
鳥インフルエンザ発生。
振り込め詐欺が横行。
夏には就職先が決定。
業種は鉄道業。
入社が翌年4月だったため、以降は悠々自適の生活を送る。
このときにプロレスや神社紹介・食べ歩きなどの個人サイトを運営し始め、神社に参拝して写真を撮影したり、いろいろ食べ歩いたりする(このサイトは2011年頃まで更新を続ける)。
新潟県中越地震が発生。
新紙幣発行。
アテネオリンピック開催。
九州新幹線新八代~鹿児島中央駅間が開業。
入社早々、JR西日本の宝塚線 尼崎脱線事故が発生し、責任の重たさを思い知らされる。
主に現場で列車の運行に携わる仕事に従事。
列車や車両の誘導・連結・切り離し・点検(入換操車)や信号扱い、運転ダイヤの管理などのほか、事務職も経験。
JR福知山線・尼崎脱線事故。
アニメ『ドラえもん』の声優が交代。
ライブドアのフジテレビ買収騒動が発生。
のちに子供が3人生まれる。
広島県 福山市に引っ越し(現在も居住)。
ボクシング内藤大助対亀田大毅の試合で亀田の反則騒動が発生。
藤原紀香と陣内智則が結婚。
裁判員制度の開始。
マイケル・ジャクソンが死去。
酒井法子が覚せい剤取締法違反で逮捕される。
HTML5・CSS3・JavaScript・jQuery・PHP・Wordpressなどについて学ぶ。
Web制作の学習により、Web制作職への転職を希望したためと、遠距離通勤に疲れたこと、いずれ遠方への異動がさけられないことなどが理由。
北陸新幹線 長野〜金沢駅間が開業。
マイナンバー制度の開始。
FIFA女子サッカーワールドカップがカナダで開催、日本が準優勝。
Apple Watch発売。
そこで少しでも実務経験をつけるべく、アルバイトや短期契約の仕事、知人の業務の手伝い、クラウドソーシシングなどでWeb制作の仕事を行う。
主にフロントエンドまわりのコーディングや画像編集、デザイン、SEO対策、ブログ記事執筆など。
また、当ブログを開設。
SMAP解散騒動が発生。
リオデジャネイロオリンピック開催。
清原和博が覚せい剤取締法違反で逮捕される。
ゲーム『ポケモンGO』が流行。
もともとクラウドソーシシングではWeb制作(コーディング)をメインとしていたが、自然とライティング業務の受注が増え、ライティングがメインに。
前年後半に開設したブログを本格的にはじめる。
2017年10月に開業届を提出。
任天堂が新型ゲーム機『ニンテンドー・スイッチ』を発売。
稀勢の里が19年ぶりの日本出身横綱に。
将棋の藤井聡太が最多連勝記録を30年ぶりに更新。
お土産紹介サイト『OMIYA!』や観光地紹介サイト『TABI CHANNEL』、グルメ情報サイト『はらへり』、神道・仏教の情報サイト『DATEMAKI (現在 休止中)』などで記事を執筆。
アサノを語る上で外せないキーワード
活動コンセプト
- 地元(岡山県、備後地方)を中心に、地域の文化や歴史を次世代に継承する活動を、ブログ運営・ライティング・写真撮影などを通じておこなっていく。
- 岡山県と福山市など備後地方におよぶエリアを、一体的な文化エリアとして世に認知させ、地域活性化のベースとする。
- 都道府県という行政の枠組みにとらわれない地域文化を広める。
得意なこと・好きなこと
ライティング
2017年から本格的にライティング業務をおこなっています。
執筆対象に対して、調査を徹底して執筆していくのが得意。
いわゆる「深掘り」に定評があります。
また、現地調査や文献調査など、調査力・取材力の高さも特徴。
「調査力」「取材力」に加え、後述の写真撮影などを組み合わせた記事づくりが武器です。
そのため特定地域の歴史・文化に関するライティング実績があります。
- 観光地を歴史背景や地理的側面、文化面から調査して執筆
- 土産菓子を地域の歴史・文化や伝統などの面から執筆
 非公開: 広島県福山市/岡山県のライター・アサノの仕事内容、仕事のご依頼
非公開: 広島県福山市/岡山県のライター・アサノの仕事内容、仕事のご依頼
もともとは、Web制作の仕事をしていたときに副業として、クラウドソーシシングでコーディングなどの仕事を受注していました。
しかし、次第にライティングの受注の比重が大きくなっていき、今ではメイン業務に。
Webサイトの「箱」をつくることから「中身」をつくる方へシフトしていったイメージです。
そのような経緯から、Web制作者側と連携をしながらの記事作成も可能。
私のストレングスファインダーを見るとわかりやすいと思いますが、私はとても好奇心が強い人間です。
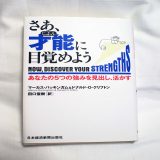 全項目を公開! 当サイト筆者のストレングス・ファインダーの結果!!
全項目を公開! 当サイト筆者のストレングス・ファインダーの結果!!
興味を持ったことには、積極的に調べたり学んだりします。
ライティングという仕事は、そんな私の特徴と相性がよい仕事なのかもしれません。
写真撮影

2004年にはじめた神社紹介の個人サイト運営を機に、写真撮影をはじめました。
サイトにのせるための神社の写真から始まり、その後は歴史的町並や史跡・名所などの撮影に広がります。
子どもが生まれたのがきっかけに、福山出身の写真家 松井紀子氏の写真教室に通って撮影を学びました(2016年までほぼ毎回参加)。
最初はコンパクトカメラで撮影していたのが、次第に自身の撮影に合う機材を求めるようになり、一眼レフカメラを購入。
その後、子どもが動き回ってくると、レンズ交換できて機動力も生かせるカメラの必要性を感じ、ミラーレス一眼カメラに乗り換えました。
その後、Webサイト制作の仕事をはじめましたが、そこで写真撮影の経験が役立ちました。
現在は、土産菓子紹介サイトの『OMIYA!』でライティングの仕事をしていますが、菓子の写真撮影もおこなっています。
OMIYA!では、ライター自身が執筆記事の画像を撮影しているので、ここでも写真撮影の経験が生かされました。
また、観光情報サイト『TABI CHANNEL』では、自分で取材し撮影した写真を使った記事も執筆しています。
このように、写真撮影では神社・仏閣や史跡・名所、町並、食品などの写真撮影が得意です。
また、現在は撮影した写真をより魅力的に仕上げるべく、画像補正を勉強中。
インスタグラムでは、グルメの写真にくわえ、神社・仏閣や史跡・名所、町並の写真をメインに公開しています。
新たに撮影した写真に加え、過去に撮影した写真を画像補正で雰囲気を変えて投稿したりしていますよ。
ASANO (@yosukay) * Instagram photos and videos
164 Followers, 370 Following, 401 Posts – See Instagram photos and videos from ASANO (@yosukay)
数年間、写真撮影をしてきて「写真は伝達の手段」であると最近になって再認識しました。
その伝達とは「意志の伝達」「情報の伝達」「記録の伝達」。
そのために、撮影時にどうしたら見た人に伝わるかをすごく考えるようになりました。
また撮影後にも、うまく伝わる写真だろうかと反省することも多く。
それは仕事で写真を多く撮影するようになったこと、まわりに写真撮影で活躍している人が多くなったことが影響しているからと思います。
写真は伝達の手段、だから伝えるために工夫することに今は力を入れています。
なお、当サイトで使っている写真は、特に表示のないものは全て私が撮影したものです。
サイト運営、コーディング(HTML/CSS)
2002〜2003年にWeb制作(HTML、CSS、Dreamweaverなど)を学習。
また2004年から2011年頃まで神社めぐりやプロレスなどをテーマにした個人サイトを運営していました。
さらに2015〜2016年にかけてHTML5、CSS3、Dreamweaver、Wordpressなどを学習。
2016年から20017年までWebサイト制作の仕事に携わりました。
そこでは主にコーダーとしてHTMLやCSSのコーディング作業をメインに、デザインや画像加工、ブログ記事執筆、SEO対策など幅広い作業を行っています。
また2016年後半からは、このブログの運営を開始しました。
これらの経験は、現在のWebメディアをメインとしたライティング業務でもおおいに役立っています。
福山市周辺(備後)エリアと岡山県の繋がりをもっと深めたい
私は岡山県で生まれ育ちました。
そして現在は広島県福山市に住んでいます。
福山に住みだしてからは10年以上経過しました。
福山市を中心とした広島県の南東部は通称「備後(びんご)地方」と呼ばれています。
岡山県と備後地方は今も昔も一体的な経済・文化圏を形成。
しかし県境という政治的に作られた枠組みにより分断され、特に備後地方はその魅力を生かしきれていません。
都道府県の枠組み自体が、経済圏や文化圏を考慮されてつくられていないからです。
私は地理や地域文化などを調べてきてそう思いました。
また私はずっと人の流れやモノの流れに携わる仕事をしてきました。
だから、経済・文化・地理・歴史などの側面で福山市周辺は本当に岡山県側とのつながりが深いのが実状だということを目の当たりにしています。
行政、およびそれを基準とした枠組みのマスコミなどだけが実状とちがうのです。
だから人間でいえば心と体が分離してしまったような状況となって、福山の力が発揮できていないのではないか?そう考えるようになりました。
その考えから、当サイトでは県境にとらわれない「吉備」のエリア=岡山県+福山市周辺(備後地方)の魅力を発信することで、行政の枠組みにとらわれない、住民の生活実態・経済状況にあった地域活性を後押ししたいと思います。
地域の文化や歴史・伝統などに興味
地名や地理が好き
元々、地元を中心とした地域の文化や歴史に興味があり、調べることが好きでした。
それを突き詰めると、地名にぶつかります。
地名は地域というものが存在する限り、地名もまた大小のいろんなものが存在しているのです。
その地名の由来はなんだろう?と自然と調べていくようになりました。
また古い地名は地形に由来していることも多く、自然とその地に足を運び、地形と地名を比べてみたりするように。
こうして地域の地理・地形などにも興味を持ちました。
くわえて、私の出身地の総社市には高梁川という大きな河川が流れています。
かつて総社平野で高梁川が東西に分かれていました。
今では東の流れは跡形もありませんが、その流路を推定してみたいと考えています。
これも地理・地形に興味を持つきっかけとなりました。
さらに2000年代に国の方針のもと、平成の大合併が全国で実施されました。
この中で多くの地名(自治体名)が消滅したり、不自然な地名・自治体名が生まれたりしました。
地名は文化遺産だと、このとき私は思うようになり、地名を遺産だと世間に認知してもらうにはどうすればよいのか考えるように。
その結果として、ブログを通じて個人で発信していくのもひとつの手だな、と考えるようになり、当ブログの運営に至りました。
古い町並や秘境的なスポットが好き
2004年からはじめた神社めぐりのサイト。
神社をいろいろとめぐっていくうちに、以下のような地域が存在することに気付きました。
● 町並み保存地区に指定されていないけど、古い町並みが残っている地域
● 建物は歴史的なものではないけど昔の風情を残している地域
自然とこのような町並みを撮影対象とするように。
同時にその町の歴史も調べるようになり、地名由来調査とつながるようになりました。
町並み保存地区でない地域は、今後失われていく可能性があります。
それを残しておきたい、多くの人に知ってもらいたいと思っています。
また、廃墟や、人里離れた隠れスポット・秘境的スポット、行事・イベントなどにも興味が向くようになりました。
まだ知られていない歴史的な場所・魅力的なスポット・イベントなどをご紹介していけたらと思います。
神社や神道に興味
私のWebサイト・ブログ運営の歴史は2004年の神社めぐりのサイトからはじまりました。
なぜ神社めぐりなのか?
それは地域の文化・歴史そのものだからです。
全国に大小の数え切れないほどの神社があるのは、ご存じの方も多いでしょう。
日本の神様は、一部がなくなった人ですが、その多くが「自然」です。
つまり自然と対等に、持ちつ持たれつで生きてきたのです。
そして人と自然が対面する場所が神社だと思います。
地域があるということは人が住んでいるということ。
人が住むということは、自然と共生するということ。
だから各地に神社があるのです。
地域と神社はセットのようなものです。
だから神社を知ることは、地域を知ることでもあるのかな、と思います。
そのため、地域の歴史に興味を持っていた私は、まず神社めぐりから始めてみようと考え、神社サイトの運営に至りました。
食べ歩きが好き、名物・銘菓など地域の食文化に興味
昔から食べることが大好きでした。
大人になり車を持つと、いろんな店を食べ歩くように。
神社めぐりサイトの姉妹サイトとして食べ歩きメインのブログもやってました。
好きな食べ物ですが、特にラーメン・うどんなどの麺類、カレー、丼物などが好きです。
ほかにも好きなものはたくさんあります。
一方で嫌いなものは物心ついたときからありません。
身体に悪影響を及ぼすものくらいです。
大きくなっても「嫌い」を理由に食べ物を残す大人が多いのは、たいへん驚いています。
その後、地域の文化や歴史に興味をもってからは、少し方向性が変わります。
単においしいものを食べるのではなく、地域の名物や銘菓など、地域に根ざしたものに興味を持つように。
食べるだけでなく、どのような歴史があるのか、どうしてその地域に定着したのか、どんなお店が提供しているのか、といったものまで調べることに面白さを感じました。
一時期、神社めぐりサイトの派生サイトとして地元の名物を紹介するページを運営していました。
しかしご当地グルメブームがおこり、各地のご当地グルメがいろんなところで紹介されるようになり、自身の名物紹介ページの意義を感じなくなり更新を停止。
でも、地元に関していえば、誤った情報が流れていたり、有名なものや話題になりそうなものばかりに情報が偏っていたりしていて疑問に思うように。
また知られていない地域の食べ物の中には消滅の危機に瀕しているものあったり、実際に消滅してしまったものもあることを知りました(水島・中田酒造の「歓びの泉」など)。
地域の食文化を少しでも残したい、そのために多くの人に知られるきっかけをつくりたいという思いで、このブログで地元を中心とした名物や銘菓を紹介することにしました。
いまではそれと並行して、自分が良いなと感じた飲食店の紹介もしています。
ライターの仕事をはじめてからは、全国の土産菓子を紹介するサイト「OMIYA!」で記事を書かせてもらえるようになりました。
こちらでも地域の銘菓を残す手助けができればと考えています。
プロレス
90年代初頭からのプロレスファンです。
ひとつめのきっかけは、1991年夏の新日本プロレス『G1クライマックス』という大会。
当時、新日本プロレスは土曜日の夕方で、視聴しやすい時間で放送されていました。
夏休みの土曜の夕方に、そのG1クライマックスの優勝決定戦が放送されていたのをたまたま見ました。
蝶野正洋が武藤敬司を下し優勝、さらに2人に橋本真也を加えた「闘魂三銃士」が活躍しました。
夏休みが開けて、友達がこの話題をしてきて、多くの友達がこれを見ていて、一気にプロレスファンの輪が広がりました。
私もこの輪の中に入り、プロレスファンとなったのでした。
2つめのきっかけは、翌1992年の夏、全日本プロレス中継です。
当時は全日本プロレスは日曜日の深夜に放送していたので見る機会はありませんでした。
しかし、夏休みの終盤に宿題が貯まっていた私は、日曜の深夜に必至に宿題をしていました。
そのときたまたまテレビをつけていて、放送されていたのが全日本プロレス中継でした。
その試合では三冠ヘビー級選手権が行われていて、王者スタン・ハンセンに三沢光晴が挑戦していました。
そして、三沢が渾身のエルボー・バットでハンセンを下し、見事王座を奪取しました。
いままで新日本プロレスしか見ていなかった私は、一気に三沢と全日本プロレスに引き込まれていきます。
夏休みが開けると、なんと友人たちも同じくその試合を見ていたのです。
以降、私と友人たちは全日本プロレスファンとなったのでした(新日本プロレスももちろん引き続き見ていました)。
もともと小さな時に『キン肉マン』が流行し、プロレスに関する予備知識は持っていました。
またその頃はゴールデンタイムでプロレス中継が行われていたり、前述のように80年代後半〜90年代前半は新日本プロレス中継が土曜夕方に放送していたりと、興味が無くてもプロレスの情報が入ってくる時代でもありました。
そのようにプロレスを好きになったのは、プロレスに関する土台を持っていたのもあると思います。
2004年に神社めぐりのサイトをはじめると、少し遅れて趣味であったプロレスのサイトも運営するように。
国内の主要プロレス団体の王者変遷をつづっていくサイトでした。
当時は各団体の公式サイトにはあまりそういう記録的な情報が少なかったからです。
しかし次第に各団体のサイトの内容が充実してきて、私がサイトに記録していく必要性が薄く感じるように。
そこでサイトを大幅縮小し、更新も控えめになりました。
元 鉄道員
ストレングス・ファインダー
ストレングス・ファインダーの結果は上から順に「最上志向」「学習欲」「内省」「収集心」「未来志向」。
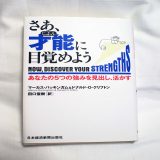 全項目を公開! 当サイト筆者のストレングス・ファインダーの結果!!
全項目を公開! 当サイト筆者のストレングス・ファインダーの結果!!
おすすめの記事
当サイトについて
当サイトは2016年11月に「風来記」の名称でスタートしました(本格稼動は翌年1月から)。
メインテーマは「地名」。
地名とは土地・地域の名前。
土地・地域に名前があれば、人の生活があります。
人の生活があれば、文化があり歴史があります。
当サイトは「地名」の由来や謎を、資料・文献を参考にするとともに筆者独自の考えの下に紐解いていきます。
そして地名をメインテーマに、地名とともに地域に眠る歴史や文化、町並や秘境、食べ物、観光、行事など人々の生活や風習を紹介していきたいと思います。
サイト運営に至るまで
実は、私は2003年頃よりサイトを運営しておりました。
当時は神社や食べ歩きに興味があったためにそれらをテーマにサイトを運営をマイペースに続けておりました。
しかし仕事やプライベートなどの環境の変化により更新頻度は次第に減っていき、参詣した神社をすべて掲載できぬまま、更新停止状態となりました。
2011年頃のことです。
その後、地名由来に興味を持ち、図書館などで文献を読み調べていました。
次第に再びサイトを運営したくなりました。今度は地名をテーマにしたものです。
しかし時代は移り変わっており、多くのサイトはWordpress、HTML5、CSS3と新しい技術を用いています。
完全に浦島太郎のような状態。
そこで一念発起し、サイト作成を再学習。
この「風来記」開設に結びつけることができました。
サイト名の由来
このサイトを構想しだした頃より私は転職など今後の私の人生をどうするか悩んでいた時期でした。
風来坊のように自分の心の赴くままに生きてみたいという思いがあり、サイト名のヒントにしました。
さらに古代において国内各国が自国の地理・歴史・風習をまためた「風土記 (ふどき)」という書物がありました。
当サイトのテーマから、風土記+風来坊で「風来記」という造語を思いつき、サイト名に決定。
運営者の経歴
1978年(昭和53年)生まれの男。
大学卒業後、21世紀初の社会人となった世代です。
食品販売の仕事などを経て、鉄道関連企業へ就職。
10年強、鉄道運転従事員や事務職として勤務します。
その後、自分の強みを生かせる分野・得意な分野で仕事をしたいと決心。
収入減を覚悟しながらも退職しました。
そしてWebサイト制作の分野でコーダー、フロントエンド・エンジニアの仕事を経験。
現在は主にライター業や写真撮影などの仕事をしています。
お仕事の詳細については下記を参照。
お問い合わせ
お問い合わせはTwitterまたはお問い合わせフォームから。